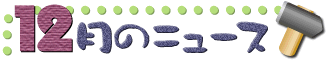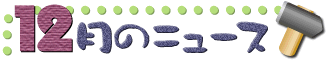医療制度改悪許すな
全建総連11.25総決起集会 |
| 「国民皆保険制度の破壊につながる医療制度改悪反対、建設国保の育成強化、国庫補助を増額せよ」をメインスローガンに、全建総連(全国建設労働組合総連合)は11月25日、日比谷公園大音楽堂で「予算要求・生活危機突破中央総決起大会」を開催し、集会後デモ行進しました。 |
国保組合守り、命守る
日比谷に6407人結集 |
 |
| 6407人が結集した全建総連11.25総決起大会 |
冒頭、前田幸太郎委員長が結集した50県連・組合、6407(東京土建は2770)人の仲間たちに「暮らしと仕事を守るため来年度予算を確保し、アスベスト100万署名を成功させよう。今日の集会を契機に全国各地域で要求実現へ運動を進めよう」とあいさつ。
つづいて、厚生労働省、国土交通省、財務省、中小企業庁への交渉団を代表して、森本文雄副委員長が決意表明しました。(交渉記事4面)
来賓として、大村秀章衆議院議員(自民)、山下八洲夫参議院議員(民主)、漆原良夫衆議院議員(公明)、笠井亮衆議院議員(共産)、福島瑞穂参議院議員(社民)のみなさんが党を代表して「281億円の建設国保補助金満額確保をはじめとする全建総連の予算要求を支持し、実現に向けがんばります」と連帯のあいさつを行ないました。
基調報告にたった佐藤書記長は「政府は医療制度改革の中で、国保組合制度の見直しをあげ、これまでの補助率にも手をつけようとしている。補助金確保とともに国保制度を守り、育てる運動を強めなくてはならない」とのべました。また、アスベスト問題では「被害者である私たち中小零細建設業者からもアスベスト補償を負担させようというトンでもない意見がある。政府と製造企業の責任で補償させ、ノンアスベスト社会の実現をめざす。耐震偽造事件の本質は建築確認の体制を民間中心にした政府の責任だ」と指摘しました。
さらに米軍再編に反対し、平和憲法を守りぬくことを呼びかけました。
宮城の佐藤惣二さん、大分の棟田忠美さんが決意表明し、「建設国保の育成・強化、大衆増税反対、憲法改悪反対、抜本的なアスベスト対策」などを趣旨とする決議を採択し、がんばろう三唱で集会を終り、常盤橋公園までのデモ行進に出発しました。 |
|
都庁集会
「国保補助金守ります」 |
| 都議会各派の幹事長が激励 |
全建総連東京都連は11月25日午前、都庁第二庁舎前に3346人の参加で「全都建設労働者対都要請行動」を行ないました。
各局、政党への交渉団を送り出して開会。まず鈴木都連委員長が「いよいよ来年度予算確保の時期に入った。建設国保への都費補助金要求も福祉保健局から財務局に提出された。予算確保へとくに自民、公明への要請をお願いしたい」とあいさつ。
佐藤全建総連書記長の激励あいさつの後、都議会会派の幹事長・幹事長代理である石井(公明)、初鹿(民主)、渡辺(共産)、大西(生活者ネット)各都議会議員から連帯のあいさつをうけました。
田口都連書記長は基調報告で政府の医療制度改悪の中で国保組合の行方は楽観できないことを強調したうえで、「都は3000億円もの税収増にもかかわらず、さらに歳出削減しようとしている。都費補助金確保へ全都議会議員の賛同署名を集めよう。地元での要請行動が国保組合を守り、育てる」とのべました。 |
|
| 広げようアスベスト100万署名 |
| 被害者の全面救済・補償とノンアスベスト社会実現へ |
 |
| アスベスト署名への協力を東京自治労連の野村書記長(左)、向さん(中)に要請する清水書記次長(手前左)、三宅常任中執(右端) |
東京土建は石綿対策全国連絡会の呼びかけに応えて、1月までに30万人の目標をかかげ「アスベスト被災者救済・アスベスト基本法を目指す」署名に取り組んでいます。この目標をやりきるため、12月15日には全都いっせい宣伝行動を行ないます。また東京地評や東京自治労連などに協力を要請しました。
署名の中身は(1)アスベスト及び含有製品の全面禁止、(2)アスベスト対策基本法の制定、(3)アスベストばく露者の健康管理制度の確立、(4)アスベスト被害の労災への時効不適用、(5)労災が適用されない被害者に労災に準じた補償の実施、(6)中皮腫すべてと、肺がん関連疾患も補償を受けられるようにすることの、6項目です。
政府は現在「石綿による健康被害の救済に関する法律案」を準備していますが、救済額は不十分なものであり、救済のための基金についてはすべての企業に納付を求めるという石綿企業の「製造責任」を不問にするものです。
政府、製造企業の責任追及、ノンアスベスト社会へ、仲間の署名協力を訴えます。 |
|
| 平和憲法・くらし守る力広がる |
悪政に共同の力結集
11.19国民大集会に3万5千人 |
 |
| 全国から3万5千人の参加で盛上がった集会 |
11月19日「憲法改悪、庶民大増税は許さない11・19国民大集会」が明治公園で開かれ、全国から3万5000人(東京土建1400人)が参加しました。集会に先立つ文化行事では、元「ニュースペーパー」の松崎菊也と石倉直樹が天皇、皇后に扮し、「もし私が民間人なら」と天皇制を笑いとばしました。松平晃のトランペットの音が会場に響きわたり、午後1時開会。
主催者を代表して熊谷金道全労連議長は「政府・財界が進める大増税の中身を宣伝し、広範な人々との共同を追及しよう」と呼びかけました。
坂本修自由法曹団団長は「決して人を殺さないという平和憲法の宝を自民党の改憲勢力に渡していいのでしょうか」と訴えました。
連帯のあいさつとして、志位和夫日本共産党委員長、山本俊正日本キリスト教協議会総幹事、芳賀裕子消費税率引き上げをやめさせるネットワーク宮城代表世話人から受けました。
全国リレートークでは、キャンプ座間への米軍司令部移転反対をたたかう神奈川の代表。農家がなーんぼ頑張ってもだめだなーと岩手農民連、沖縄の島ぐるみのたたかいを紹介した沖縄の代表、東京の高校生平和ゼミナールなど、各代表の訴えに大きな連帯の拍手が沸きました。最後に「集会アピール」を採択し、3つのコースに分かれてデモ行進しました。東京土建は代々木公園コースでした。 |
|
| 米軍基地強化反対 |
座間市で全国集会
「戦争指令部来るな」と包囲 |
「地元の意向を最大限尊重して……」と語っていた小泉首相。地元・横須賀市への連絡もなく、一方的な基地の再編・強化の押しつけに、全国から批判の声があがっています。今回は、米軍基地をかかえる各自治体の首長はもとより、住民こぞって反対するという構図に発展しています。
中でも神奈川県座間市では、米陸軍の第一軍団司令部の同市キャンプに移転させる計画に、座間市をあげて反対しています。(写真)
11月26日、谷戸山公園に全国から1万1000人が結集して、「戦争司令部くるな」と集会を開き、その後、キャンプ座間を包囲する長いデモと、午後3時30分には、花火を合図に「戦争司令部お断り」のステッカーを頭上にかざして、上空を飛ぶヘリコプターにアピールしました。 |
|
| 「多摩平和イベント」行軍で飛びいり参加も |
【多摩・稲城・書記・樋口孝治記】
11月23日、「戦後60年」多摩平和イベント実行委員会主催で集会やパレードを行ないイベントは永山北公園で開催。和太鼓や詩の朗読、楽器演奏など2時間にわたり市民グループが行ないました。(写真)
2時からは集会に変わり、「自衛隊のイラク派兵や憲法改悪の危険な動きに対して、草の根から平和の声をあげよう」と集会の意義が訴えられ、また、戦争体験者からは「二度と戦争はしてはならない」と悲惨な戦争体験が語られました。さらに横田基地返還運動の報告。大学の「9条の会」で活動する学生からの発言など、反戦、平和への思いが集まりました。
3時からは桜ヶ丘駅まで、シュプレヒコールやラップの音楽にのせてパレードを行ない、途中からの参加者もあり、住民の関心を呼び起こした催しになりました。
参加者は200人(東京土建24人)でした。 |
|
| 第12回全国建設研究交流集会 |
地域振興と再生で発言も
墨田区の政策に注目 |
11月20、21日の両日、熱海の「ホテル大野屋」で建設政策研究所などが主催する第12回全国建設研究交流集会が開催され、全国から410人(東京土建から89人)が参加しました。
後藤道夫都留文科大学教授による記念講演は「構造改革と憲法改正」と題し、急速に階層格差が拡大する日本の状況とその問題点、労働運動、地域運動の課題について明らかにするものでした。つづいての特別報告では、墨田区の高野産業政策課長が東京土建墨田支部と協力しての地域建設産業振興政策について報告し、注目を集めました。
2日目の分科会では、「震災対策と災害復旧」で世田谷支部の西田書記長が地域の町会とも提携してのとりくみを報告したのをはじめ、「アスベスト被災の実情と救済のとりくみ」、「地域建設業の振興と地域再生」、などを報告し、積極的に発言していきました。
集会は「憲法を仕事と暮らしの中に生かすため、労働協約の実現、労働災害の責任追及・発生防止、公契約条例制定、住民本位のまちづくりと仕事確保、建設人9条の会の前進」などを内容とするアピールを採択し閉会しました。 |
|
医療改悪許すな
東京社保協総会開く |
東京社会保障推進協議会(東京社保協)は11月17日、第36回総会を90人の参加で開催。政府・与党の憲法改悪や医療制度の大改悪をはじめ、社会保障総改悪を進めようとしている中で開きました。
後藤嘉輝事務局長より情勢と活動報告、午後からはカナダ視察をされた村林会長と東京土建の関根和夫さんの報告のほか、加盟団体や地域社保協の取り組み、都政問題や障害者団体など19人の発言がありました。最後に後藤事務局長から草の根の学習会を積極的にすすめ、対話をしながら運動を広げることで「今こそ社保協の出番」と強調しました。
新四役は会長・竹崎三立。副会長・大内貞雄(東京土建)ほか5人。事務局長・後藤嘉輝。事務局次長・成平正英(東京土建)です。 |
|
品川支部
沿道の注目を引く大増税阻止の地域デモ |
【品川・書記・伊藤暁記】
品川支部は、「大増税ストップ」を地域から世論に訴える運動として、11月18日夕、「11・18品川建設労働者大行動」を行ない237人が参加。地元の建設組合(東京建設、東京南部建設、建設産業ユニオン城南支部)からも参加し『提灯デモ』で地域共闘ができました。(写真)
提灯を片手に商店街を歩く仲間の姿は、沿道の通行者、商店街の皆さんの注目を引いて、行動をアピールし、デモの意義を果たせました。
今の税制改正論議の問題点は、消費税率の引き上げ、所得税の定率減税廃止等です。増税の前に、歳出削減の努力はもちろん、応能負担にもとづいた公正負担を求め、今後の増税の動きを注視し、政府に対し「大増税ストップ」の世論を示す行動をしていかなければなりません。 |
|
構造計算書の偽造問題
誰も疑問を感じなかったのか |
建築だけの問題か
仕事をまっとうする責任は |
 |
| 田中詔さん |
【渋谷・設計・田中詔記】
建物を壊れないようにする仕事の構造設計者が、法定耐力のない設計をしました。安くしないと仕事がこない、生活できなくなるから、と弁解しています。私たち職人や技術者や設計者は、それぞれ自分の仕事をまっとうする責任を負っています。
安くする工夫は、責任をまっとうすることが前提になっています。建物は専門家が協力してつくりあげます。それぞれ自分の専門分野の責任を果たさねばなりません。そうしてこそプロであり、報酬をもらえるのです。自分の生活のために、その責任を放棄してしまっては、社会が成り立ちません。ルールを破って安くするのでは、プロとしての資格を問われます。ルールを守って苦労している人の立場はどうなるのでしょう。大自然にはルール破りは通用しません。
きちんとつくる役割の工事業者が気づかなかった。現場監督も作業員も、鉄筋が少なかったり柱が細かったら疑問を感じるのが普通です。図面どおりにつくりさえすれば良いというものではありません。 |
 |
| 鉄筋作業現場(記事とは関係ありません) |
検査機関も手抜き
安く安くのプレッシャーで
作業や技術や管理が細分化され、各関係者が全体に目を配れなくなっています。マニュアルどおりを強制されて、自分自身の技術者としての良心をマヒさせられています。
広く目配りをすべき事業者が圧力をかけました。建物の発注者は、計画段階で総合的に問題を検討すべきです。この責任を十分に果たしている発注者は、ただでさえ少ないのが実情です。
まして単に安ければ良い、などという考え方は論外です。安く安くとプレッシャーをかけるなど、事業家の風上にもおけません。問題が発覚したら、政治家を間に入れて、公的資金導入の画策までしています。
チェックをする検査機関が手抜きをしました。建築確認業務が民間に開放されたため、各機関の競争が激化しています。確認申請する側は、自分に都合の良い扱いをするところに行ってしまいます。まともに審査して時間や金がかかると、よそへ行かれてしまいます。生き残り(すなわち生活)のため、本来きちんとチェックしなくてはならないことを、十分にできない状況にあります。民営機関にゼネコンやメーカーが出資しており、将来は圧力が懸念され、政治との癒着も心配です。 |
 |
| 国交省が構造計算書偽造と発表した渋谷区初台のマンション |
行政が責任を放棄
「構造改革」の当然の帰結だ
民間に丸投げするのでなく、役所の審査・検査の人材を充実すべきです。建築主事やそのスタッフは民間では補えません。
目を光らせるべき役所が弱体化されています。役所の審査でも見抜けなかったから、民営化のせいではない、というのは問題のすりかえです。こういう詭弁が今、まかりとおっています。建築基準法大改定以降、制度全体の信頼性がゆらいでいます。最低限の安全は役所が最終的に責任を持つよう、世の中の仕組みはできています。
「民間にできることは民間に」との、バカの一つおぼえの呪文が、諸悪の根源です。行政が責任を放棄する方向に進んでいる、現在の「構造改革」は日本を歪めています。国や政治の責任は重大です。住民・利用者の不安に対する相談・診断・補償等を十分にして安全を確保すべきです。
今回の事件は氷山の一角、設計や建築の分野だけの問題ではありません。背景には金がすべてという風潮があります。 |
お金で買えないもの
自分の生きざま確立しよう
こういう金がカタキの世の中で良いのでしょうか。私たちは金よりも、もっと大切なものを知っています。技術や文化や伝統など、金で買えない貴重なものが、この世にはたくさんあります。政治は本来、それらを生かす方向に進まねばなりません。そのためには私たちも、マスコミに流されるのでなく、自分自身の生きざまをしっかりと確立し、周囲に波及させていく必要があります。 |
地域に責任もつ私達
安心・安全なまちづくりめざす |
 |
| 松井民人さん |
【本部・松井民人記】
悪質リフォーム業者の詐欺行為や建材として使用されてきたアスベストによる健康被害等、住宅建築・リフォームに対する住民の不安が増大する中で耐震設計に必要な構造計算書が書類作成を請負った建築設計事務所によって偽造されるという事件が大問題になっています。
安全よりも利益を優先
マスコミの多くが下請として構造計算書を作成していた建築士へのバッシングや法的処置、またデベロッパー(開発会社)、元請施工業者の対応等を中心に報道していますが、私たちは建設業に働く者として、さらに「安心・安全なまちづくり」をめざす建設労働組合としてこの問題の本質をとらえておく必要があります。
そもそも建物の耐震性、安全面から最も重視されなければならない構造計算書を偽造した一級建築士の行為は許されませんが、最大の問題は、デベロッパーや元請施工業者などが「構造が安ければいい」として居住者・住民の「安全よりも利益を優先」したこと、さらに偽造された構造計算書を検査機関が見抜けなかったことにあります。
これまで自治体が行なってきた建築確認の検査業務は98年の法「改正」によって、翌年から国・都道府県知事が指定した民間の検査機関でもできるようになりました。「官から民へ」という規制緩和の名の下に自治体が担うべき役割を民間に開放した結果が、今回の事件の根幹にあることは明らかです。
北側国交相が「建築確認という公の事務の関与があり、純然たる民間の問題とはいえない。行政がしっかり対応するべきだ(11/22)」と発言していることからも国や自治体は、住民の生命や財産を守る役割を再認識し、「儲け」の対象となっている民間丸投げの検査業務体制の見直しを図るとともに、居住者の安全を第一に住居の保証等の対策を早急にすすめることが必要です。
悪質リフォーム業者による詐欺行為や今回の構造計算書偽造事件によって建設産業に対する社会的評価は著しく低下しています。「安全よりも利益優先」とするゼネコン中心の産業構造を変えること=「建設産業の民主化」をはかることが私たち建設労働組合の使命です。
産業民主化信頼構築を
不正行為に対して現場から告発できる産業に変えるとともに、住宅デーや耐震金具取り付け等のボランティア活動の中で「地元にくらし、地元で働く、地元の仕事に責任をもった」私たちが、地域住民との信頼関係の構築、ネットワークづくりを積極的にすすめていくことが求められています。 |
|
全建総連が各省庁へ予算要求
11.25中央総決起大会 |
建設国保を育成強化しろ
アスベストの使用を禁止しろ
午前中東京都の各局と交渉 |
 |
| 厚生労働省保険局と交渉する全建総連の代表 |
保険局
国庫補助の見直しで
18年度普通調整実施と回答
【全建総連社保対部】
金子副委員長を団長に59人が参加。保険局は唐澤国保課長を含め4人が応対。
社会保障審議会で国保組合の所得調査結果が示され、「国庫補助について、所得調査結果に基づき、見直しを検討」とされたことで、国庫補助の見直しが交渉の焦点となりました。
交渉団は、普通調整補助金(普調)が1ランク下がると全建総連23国保組合がこうむる財政負担が、月額2152円から1631円になることを説明、ランクを見直さないよう迫りました。また、「定率補助も普調も見直すのか」「普調の見直しは18年度から実施か」など、国保組合運営に重大な影響を及ぼす課題について質問しました。
唐澤課長は「定率32%と財政調整分15%枠は、手をつける考えはない」と明言。
普調の見直しでは、「医療制度改正法案を提出する18年度から実施せざるを得ない」と回答。一方で、「急激なことにならないよう、なだらかにする工夫が必要」とし、含みをもたせました。仲間からは、「7割給付の合意がやっとできたのに、次は普調の見直し。組合員の理解が得られない」「ランク見直しは組合の存続に関わる」ときびしい現状を訴え、理解を求めました。
来年度の国保組合の特別助成では「例年よりきびしい」とした上で、「生活習慣病予防の芽を盛り込みたい」と、国保組合の生活習慣病予防の新たな補助確保に前向きな姿勢を示しました。 |
 |
| 調布の主婦のみなさんもガンバロー |
労働基準局
アスベスト時効問題
労災補償に準じた措置とる
【全建総連労働対策部】
田辺副委員長を団長に全建総連から13人が参加し、厚生労働省は労災補償部補償課職業病認定対策室の伊作係長をはじめ8人が出席。次のような回答がありました。
「アスベスト被害者の時効問題については、他の疾病との公平性から特例を認めるのはむずかしいが、時効によって権利を失われた方は、周辺住民との救済とあわせて労災補償に準じた措置を講ずることとしている」。「時効の起算については、遺族であれば労働者の方が亡くなってから起算するという最高裁判決がある」。
 |
| 労働基準局には労働対策部が申入れ |
「石綿による健康被害にかかわる医学的判断についての検討会を設置し、第一回の検討会で中皮腫については原因のほとんどが石綿であると確認された。次回以降肺ガンなどについて検討を進める。その結果を踏まえ労災補償を適切に実施したい」。「びまん性胸膜肥厚は認定要件を設定できるほど症例がないため、個別に判断している」。
「現状では中皮腫治療に効能効果のある医薬品はないが、治験中の新薬アリムタについては、薬事法上の承認申請がなされれば迅速に処理していきたい」。
「手間請就労者を一律に元請労災から除外している件については、労働局・監督署の立ち入り調査で適用関係が正しく適用されていないケースが発見されれば、元請の責任の所在を指導していく」と回答しました。 |
 |
| 国土交通省には住宅建設の促進を要請 |
国土交通省
耐震改修住宅に減税要求
悪徳リフォームの相談窓口に
全建総連の協力も必要だ
【全建総連住宅対策部】
田村副委員長を団長に31人が参加。省側は12人の担当官が対応しました。
住宅金融公庫関係では「災害時等の融資は公庫廃止後も存続したい。『フラット35』普及のため、制度改善等努力を続けたい。『優良住宅取得制度』をもっと利用してもらえるよう増額要求している」。
住宅税制では「耐震改修を行なった際の減税を要求している。消費税が引き上げられると住宅には影響が大きすぎる。良質なストックとしての住宅には消費税を上げるなと主張するためにも、住宅基本法の議論をしっかり進めたい」と今までよりも踏み込んだ発言。
木造住宅の振興、「木造住宅総合対策事業」補助については必要な額を確保したいと表明がありました。
アスベスト対策では「省内に対策部会を設置した。廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法等の規制は、所管が他省だ。建材のリスト化は、石綿協会で行なっている。建材の除去作業中の曝露対策等について技術開発を検討している」との答えに、交渉団からは「石綿の耐火被覆は87年まで建築基準法で容認してきたことを脇に置いて『建築物の持ち主責任だ』と言うのは乱暴だ」。「石綿含有建材の除去工事は、14日前までに届出というが、リフォームでは直前までわからない場合がある。実態に合った施策を」と発言しました。
悪徳リフォーム対策では、「すべての市町村に相談窓口をつくる。みなさんの協力も必要だ」との回答でした。 |
中小企業庁
中小業者へ優先発注
パンフで周知はかっている
【全建総連工務店対策部】
要請は、中小企業庁の鈴木事業環境部長ほか8人に対し、安部副委員長を団長に13人が行ないました。今回も民主党の大畠章宏衆議院議員に同席いただきました。
『官公需法の遵守』『分割発注の推進』『中小建設業者への優先発注』については、「要望を受けとめ、発注の適切な事例をパンフレットにまとめて周知をはかっている」との回答でした。
『融資の担保や保証制度の改善』については、大畠議員からも、融資の審査が必要以上にきびしく行なわれている現状の問題点や、一定の『ガイドライン』の必要性が指摘され、仲間からも金融機関の対応への不安について発言し「関係省庁へも申し入れをしていきたい」との回答がありました。
また、『新会社法』についての意見交換も行ない、仲間からの「中身がわかりづらい」との発言に対し、「説明会等のご連絡をいただければ、本庁から説明員を直接派遣して説明させていただき、適正な周知につとめたい」と回答がありました。
今後もお互いに意見交換をはかりながら、中小建設業者の健全経営を確認して終了しました。 |
財務省主計局
負担が増えれば死活問題
医療改革と予算編成が同時進行
国保組合の運営努力は理解する
【全建総連税金対策部】
財務省主計局の谷内企画官が対応。全建総連からは棗田副委員長を団長に、里見税対部長ら20人が交渉に参加しました。
谷口企画官は厚生労働省の給付率見直し資料を見ながら、「医療制度の抜本改革と予算編成が同時並行に行なわれている。財務省としても社会保障費の自然増を含め日本の財政は逼迫しており、制度的にも財政上からも将来持続可能か不安がある。厚生労働省の医療制度改革の試案にも国保組合を適切に見直すとあるように、補助金についても厚生労働省と話しあいをしている」とのべました。
代表団は「必死で保険料を払い、他の国保組合にくらべ徴収率を上げている」「健康診断やレセプト点検を徹底し、医療費削減に努力している」「給付ランクを1%さわられるだけで、組合員の負担が大きい」「負担が増えれば国保組合、母体労組は死活問題」「地震等の災害復興等の地域活動にも寄与している」と訴えました。
企画官からは「運営努力は十分理解している。国の財政は大変きびしいが、必要なところには予算をつけ、緊急性のないところとはメリハリはつけなくてはならない。国保組合にもいろいろあるが、どうするかは今後の厚生労働省との話しあいでつめていきたい」とのべました。 |
 |
| 福祉保健局に補助金の現行水準確保を要求 |
福祉保健局
財務に現行水準要求
国保組合の健全運営考えて
【本部・百瀬文治記】
東京都福祉保健局交渉は、都側から秋好国保課長ほか3人が出席、組合側は、鈴木都連委員長、田口都連書記長、松尾都連社会保障対策部長ほか都連傘下の各組合、国保組合より107人(東京土建67人)が参加して行ないました。
秋好国保課長は財務局への福祉保健局としての国保予算要求額について「昨年が71億6779万4千円、被保険者数が減っているということがあり、金額で前年を超えるということはなかなかむずかしい。いろいろ加味しなんとか予算が通る金額として今年度は70億5941万6千円を要求しました」と具体的な数字を明らかにしました。
総額では前年より若干減少したものの被保険者一人当りの補助金の額では現行水準を維持しているとの説明がありました。参加者から「建設労働者にとって建設国保はまさに『命の綱』となっている」「賃金が下がり生活も困難になるなかで毎月の保険料納付に努力している」「都の補助金が減らされれば直接保険料にはねかえり生活できない」など切実な訴えが出され、これを受けて秋好国保課長は「国保組合の健全運営を念頭から離すことなくいきたい」と締めくくりました。 |
産業労働局
「公契約条例必要ない」
現場の賃金知ってるかと反論
【本部・唐澤一喜記】
産業労働局交渉は、東京都連高野賃金対策部長を団長に20人(東京土建11人)が参加。建設労働者の適正賃金・単価の確保、ダンピング受注防止、建退共の普及について要望しました。都側から財務局の担当者が公契約について答弁し、「労働基準法、最低賃金法等の労働関係法規があるし、ILO94号条約を国が批准していないことから、制定する必要がない」と発言。
交渉団は「東京都議会や201の自治体でも意見書を採択している。契約課は情勢の認識が甘い。行政は末端で働くわれわれの賃金を知っているのか」と詰め寄りました。
入札・契約問題では「平成15年より施工体制調査を行なっている。立入点検は検討していかなければならない。入札の総合評価も検討している」と答弁。交渉団は適正品質を安い賃金で確保することはできない。都発注現場でも不払いが多発し、低入札を是正するなど契約のあり方を考えるべき、と追及しました。
建退共問題では、知事名で加入促進の通達を出している。組合が行なう建退共説明会は差しつかえない。連鎖倒産防止対策では、下請業者が融資を受けやすくなるようサポートしている、と回答。 |
 |
| 都市整備局に申入れる交渉団 |
都市整備局
住民避難の耐震助成検討
多摩産材には優遇利息
【本部・船越宣樹記】
都市整備局は東京都連合理化対策部・清水部長を先頭に22人の参加で行ないました。
冒頭、清水部長は「この数年、都段階で耐震工事の助成制度が切望されている。新しくできた国の地域住宅交付金制度の活用などでぜひ実現させていただきたい。今回から工事代金・賃金の不払い問題もこの場で交渉することになった。耐震偽造問題の木村建設は再三にわたり不払いを起こしている企業だ。低価格で受注し結局は不払いにつながる。各要求項目に積極的な対応を期待している」とのべました。
主な要求項目は、(1)木造を含む個人住宅への耐震診断・改修助成制度の創設、(2)地元産材の活用、(3)住宅デーへの支援、(4)バリアフリー化への助成、(5)倒産・不払い対策などでした。
耐震改修助成について都側は、「地震発生時に住宅が倒壊して住民が避難できなくなるような地域に対して助成制度を検討中だ。公共性の高い企画として来年度の予算要求に出している」。
地元産材の活用については「多摩産材を50%以上活用した場合、低額利息で優遇するように金融機関と交渉している。12月中に動き出したいと考えている」と、いままでより一歩踏み込んだ回答がなされました。 |
参加した仲間の声 |
 |
| 廣間さん |
来年3月にパパになります
【板橋・床内装・廣間隆太さん談】
2年前組合に入り、初めて集会に参加しました。全国から参加しているのでびっくりしました。
来年3月子どもが生まれます。消費税の増税やられたら本当に困りますよ。組合に入って結婚のお祝い金もいただき、今度は出産でもいただけるときき、がんばらないといけないと思います。車の保険も組合に変えました。 |
 |
| 谷口さん |
女房が手術で助かりました
【武蔵野・ハウスクリーニング・谷口哲士さん談】
前に女房が乳がんの手術をして、土建国保のおかげでほとんどお金がかからず助かりました。これも組合ががんばっているからだと感謝しています。私も組合のお役に多少とも立ちたいと、ここ2〜3年支部の役員もやってすこしずつ組合もわかってきました。
それで、うちの従業員も組合加入させました。 |
|
仲間と語る
伊藤委員長に説得されて大工職人から組合専従の道に |
| 組合結成から60年、12万5千人の東京土建にはさまざまな仲間がいます。その時どきのテーマや話題にそって、自由におしゃべりをしようというのが、この「仲間と語る」のページです。これからは一カ月か2カ月に1回は掲載します。再開第一回は、元本部書記長で、現在は「建設人9条の会」の運営委員長として活躍中の荒井春男さんです。 |
 |
| 荒井春男さん |
「職人にも健康保険を」
荒井春男さん活動の第一歩
「御国のため」
予科練に志願
‐荒井さん、たしかお生まれは東京でしたよね。
荒井さん そう国分寺の工務店の長男坊で昭和2年生まれ。男4人、女4人の8人兄弟と、おやじの3番弟子が住み込みでいました。
‐じゃあ、大工になるのはごく自然だったですね。
荒井さん そう、地元の高等小学校を出てから、おやじの手伝いをしながらね、御茶ノ水にあった日大工業学校の夜間に通ったんですよ。そうしたら、昭和19年大講堂に集合がかかったんですよ。何ごとかと思ったら、海軍予科練の「七つボタンの桜に錨」の白い制服を着た先輩が戦局をとうとうと説き、「われらに続け」と、志願を呼びかけたんですよ。
‐それで、志願して予科練に行かれたんですね。荒井さんは長男だし、戦局は不利ですから、お父さんは反対されませんでしたか。
荒井さん 内緒で受験したから、おやじは合格通知がきてはじめて知ったんですよ。本当は反対だけど「御国のために志願」している息子をとめたら、自分が「非国民」になっちゃうから、反対できなかった。
‐荒井さんはたしか航空兵でしたよね。
荒井さん 正確にいうと所属は海軍三重航空隊奈良分遣隊で身分は海軍甲種飛行予科訓練生です。偶然、小学校の同級生の桜井くんー彼とは戦後も縁が続くんですがーも同じ分隊だった。そこから、静岡の三保の松原に移った。こんどは第15嵐部隊で、特攻艇「震洋」です。毎日アメリカのB29が京浜地帯の空襲に悠然と上空を飛んでいき、静岡は艦砲射撃される。それに対しこちらはベニヤ製の特攻艇ですからお話にならない。これはだめだと思いました。
‐では8月15日の終戦もショックではなかったですね。
荒井さん それが終戦から2、3日して国分寺の実家に帰ったんだけど、何をする気にもならなかったですね。まあ、予科練帰りは左翼になるか、闇屋=不良になるか、どちらかでした。私は左翼になったほうで、山辺健太郎さん(戦前からの労働運動家)なんかの指導で「米よこせ」の運動をやったんです。お得意の手前、おやじはいやな顔するし、家内のよし子と知り合ったこともあって、家を出て結婚したんです。 |
 |
| 荒井さんが初めて本部役員に選ばれた東京土建第9回大会(1955・国労会館) |
背広なく借り着で出席
28歳・第9回大会で中執に
旧友が東京土建の書記局に
‐東京土建との出会いはいつごろになります。
荒井さん 1951年に息子が生まれ、小児喘息の発作で死にそうになった。立川病院に入院して手術をうけたんだけど、健康保険がないものだから、10日ごとの支払いが稼ぐ手間以上になってしまう。同室の人が「建設職人は大変だね」と同情してくれて、「職人にも健康保険をと運動している組合がある」と東京土建を教えてくれた。息子が日赤に転院するので青山に引っ越して、中央支部(当時)を訪ねていったら、そこの書記がなんと小学校、予科練で一緒だった桜井くんだった。
‐それは奇遇ですね。
荒井さん 喘息入院の息子を抱えて、稼がなくてはならず、組合活動に積極的に参加するようになったのは日雇健保獲得決起集会(1952年9月)からです。1955年の第9回大会で中央執行委員に選ばれました。まだ28歳の一職人でした。役員に選ばれるのだからと、背広をもっていませんでしたから、借りて着ていきました。
‐はじめは教宣部長をされたのですよね。
荒井さん 弁当も包めないような新聞じゃだめだ、といきなり「けんせつ」を朝日や読売のような大版の新聞にして、「勝手なことをするな」と伊藤清委員長(当時)に叱られたりしましたが、教宣部を担当して、組合活動が隅々まで見えるようになったと思います。 |
「建設人・9条の会」発展させ平和憲法守る |
仕事確保運動に全力
「大工代表」の思いを胸に
‐専従役員になられたのはいつでしたか。
荒井さん 59年の9月です。それまでは自分の工務店を起こして、社長になろうと思っていたのですから、「専従に」と言われて迷いました。どこで聞いたのか、おやじが出てきて、「お前はオレの相続人だぞ」と反対する。それでも組合専従になったのは、伊藤委員長の「自分のことでなく、建設職人みんなのことを考えなければいけない」とさとされたからです。
‐その後、東京都連事務局長になられましたね。
荒井さん この時も伊藤さんから「若いときに苦労はするもんだよ」と説得されました。当時の都連は派閥があって幹事会できめても実行されない。そこで西部建設の須田進吾さんと組んで、書記の村井隆雄さん(後に都連書記長)にもあちこち奔走してもらって執行委員会体制に変え、初代書記長になりました。
‐東京土建に戻られてからの荒井さんは住宅デーはじめ住宅問題、技術のエキスパートになられましたが。
荒井さん 高度成長期に住宅メーカーが地域工務店の仕事・職域を奪っていく。もっと仕事確保の運動をやるべきだと思って、全建総連でもそう発言したのです。そうしたら唐沢平治さん(元全建総連書記長)が「じゃあ、あんたがやれ」と、全建総連の住宅対策部長にされた。建設職人のマナーを定めた「職人憲法」の学習運動をやりましたが、職人はやはり体を使って運動をしなくてはだめだと、住宅デー運動を提起したのです。
‐東京土建本部書記長もつとめられましたが、「工務店の社長になったほうがよかった」と後悔したことはないですか。
大工道具手放し覚悟きめた
荒井さん 昔の仲間に冗談で言ったことはあるけれど、思ったことないですね。専従になって間もないころ、私が大工道具を大切にしまっていることを知った伊藤さんから「道具を大事にしているのなら現場に戻りなさい」と叱られ、弟たちに譲りました。覚悟ができていないという意味だったからです。「あなたがだめだったら、だから大工出身はダメだと言われるのですよ」ともよく言われました。杉並の小木勝三郎さん(元本部副委員長)からも「お前は大工の代表なんだぞ」と励まされ、支えられましたから。
‐私生活のことで恐縮ですが、退職後はおくさんの介護をされましたね。
荒井さん 骨粗しょう症で動けなくなった家内を5年ほど介護しましたかね。まあ、苦労をかけ、家のことは何もしなかった昔の罪滅ぼしですよ。動けなくても家内が生きていてくれればいいが、先立たれてしまうと、男はさびしいものです。
‐さて、最後になりましたけれど、「建設人9条の会」について、抱負と決意を。
荒井さん アンケートを見ても今の若い人は平和憲法は大事だと思っている。しかし、経験がないからどう運動していいのかがわからない。そうした若者と、私たちの労働運動、大衆運動の経験を結びつけたい。建設関係の「9条の会」を大きくまとめて、平和憲法を守りぬく、これが私の最後の運動だと思っているんです。
‐東京土建の仲間も一緒にがんばりたいですね。今日はありがとうございました。 |
|
受け入れ態勢が不備
深刻なアスベスト廃材処分 |
| アスベスト混入建材の廃棄物を引き取ってもらえない、立方メートルあたり2万5千円〜3万円以上と値段があまりにも高すぎる、という仲間の切実な声が寄せられています。年の瀬にかけて処分問題がさらに深刻になってきます。組合では国や都などへ働きかけをおこなってきましたが、東京都が年内に解決する動きが出てきました。 |
 |
| 深刻なアスベスト混入建築廃材の処分問題 |
【仕事対策部発】
最近、本部に「アスベストが混入している廃棄物を引き取ってもらえない」という問い合わせがよくあります。
仲間のみなさんはいままでも安くない処分費用に頭を抱えていたうえにこんどはアスベスト処分が法律で決められ大変な状況です。しかしアスベストは命にかかわる問題ですし住民にも安心できる対策と説明が必要です
とはいえ、はじめにのべたように、特に新規の持込みに対して、中間処分場は「引き取れない」とことわったり、立方メートル3万円以上の値段を提示する場合もあるとのことです。このように受け入れ態勢ができていないことは本当に切実なことです。
本来、法律では「アスベスト混入の非飛散性廃棄物」は一般の建設廃棄物として処分が可能です。(ただし、破砕して飛散しないように取り扱うこと)環境省や都では業界団体を通じて飛散防止設備のない処分業者は破砕しない旨の指導は行なっているようです。
したがって、中間処分業者は法律上「引き取れない」ことはないはずですが、「保管スペースや破砕設備がない、破砕しなければ最終処分場が引き取らない」などの理由で引き取らない、値段が高いなどの状況が生まれています。
11月25日の全都建設労働者対都要請行動でこの切実な要求について交渉しました。だいぶ問い合わせもある様子で、「都としてもいま動いている。中間処分場や最終処分場の指導をおこない年内には解決したい」との回答でした。 |
|
増収・増益の大手
5社とも1兆円超受注 |
11月28日の日刊建設工業新聞は、05年9月中間決算について、建設業主要27社のうち26社の連結業績で3分の2の17社が増収となり、景気回復で堅調に推移した民間工事の受注増などが増収に寄与したと分析。大手5社で見るとこの半期の売り上げ(前年同期比)順では、大成建設が5906億円で12・7%増。大林組は5906億円で7・9%。鹿島は7844億円で7・1%増。清水建設は5555億円で0%の微減。竹中工務店は(6月中間決算・参考)6225億円で8・2%の増です。
準大手の前田建設は1567億円の21・7%。長谷工コーポレーションは2578億円で14・2%と大きく伸ばしています。一方、利益確保のため、受注の多様化を図る傾向もあるとしています。
06年3月期の予想売り上げでは、5社とも1兆7000億円の鹿島を筆頭に、通期の業績は17社が増収を予想し、全社が経常黒字を見込み、このうち16社が増益を予想。こうした結果は“利益競争”で仲間の賃金・単価を抑えこんでいる大手の1人勝ちが鮮明になっています。 |